「関東大震災」
1923年9月1日11時58分32秒に発生したマグニチュード7.9の地震(関東大地震)によって、南関東および隣接地で大きな被害をもたらし、105385人の死者・行方不明者が発生しました。全潰全焼流出家屋293,387に上り、電気、水道、道路、鉄道等のライフラインにも甚大な被害が発生しました。明治以降の日本の地震被害としては最大規模の被害となりました。
神奈川県および東京府(現:東京都)を中心に隣接する茨城県・千葉県から静岡県東部までの内陸と沿岸に及ぶ、広い範囲に甚大な被害をもたらしました。一般に大震災と呼ばれる災害ではそれぞれ死因に特徴があり、本震災では焼死、阪神・淡路大震災では圧死、東日本大震災では溺死が多くみられました。本震災において焼死が多かったのは、日本海沿岸を北上する台風に吹き込む強風が関東地方に吹き込み、木造住宅が密集していた当時の東京市(東京15区)などで火災が広範囲に発生したことによります。正午前ということもあり、食事の準備のために火を使っている家庭も多く、強風や水道管の破裂もあり、火災が3日間続きました。近代日本において史上最大規模の被害をもたらしました。
関東南部、特に神奈川県西部及び千葉県の房総地域においては、地震やその直後の大雨により、崩壊や地すべり、土石流などによる土砂災害が多数発生し、に今の小田原市根府川では土石流により埋没64戸、死者406人という被害が発生しました。東京湾岸部の干拓地や埋め立て地、相模川、荒川、古利根川などの河川沿いの低地においては地盤の液状化が起こり、地盤の陥没や地割れ、建物の沈下、傾斜、地下水や砂の噴出などの現象が起こりました。
本当に、二度と起こってほしくない、起こしてはならない出来事となりました。犠牲になられた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。追悼の意を込めて、「決して忘れてはいけないこと」、「決して忘れてはいけない災害」として、 Never Forget Number 105385 を掲載致します。
震災後、東京市電の機能不全を肩代わりさせるため、東京市がT型フォードを約800台輸入してバス事業を開始(円太郎バス)し、全国にバス事業が広まると、輸入トラックを利用した貨物輸送も始まり、現在にも続く、旅客および物流におけるモータリゼーションや、通信手段の中心となる電話の自動交換機も、この地震の復興の中で普及しました。







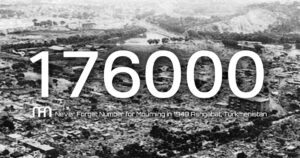
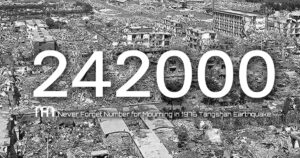


コメント